「♪キン・キン・キンタマリンの ナ・ナ・フ・シ・ギ!」
いきなりこんなんでスマンスマンスマン。
ご存じ「軍艦マーチ」こと『軍艦行進曲』だが、自分が小学生のころ、こんな替え歌が流行っていた。
軍歌のはずなのに普通に替え歌が通用するほど、昭和生まれの小学生には身近な曲だったってことだ。
パチンコを題材にしたコミックソング『ひらけ!チューリップ』(間寛平/1975年)の冒頭でも軍艦マーチが流れているように、パチンコ屋の定番BGMというのが当時の世間一般の表題曲に対する認識だった。
もちろん小学生当時パチンコ屋なんかに出入りはしていなかったけど、どういうわけか皆同じ認識を持っていたと思う。
で、おそらく、「パチンコ」→「チンコ」→「キンタマ」的な小学生大喜びパターンからきているのだろう。冒頭に紹介した替え歌が我々の間で流布していた。
どうでもいいことだが、冒頭の歌詞は、軍艦マーチの威勢のいい前奏部分に当てはまり、本来歌詞がある「♪守るも攻めるも・・・」の部分は、次のような歌詞だった
♪ゴムでもないのに伸び縮み 直径2センチ金の玉
♪取られてたまるかソーセージ しぼれば黄色いお茶が出る
内容はひどいけど、小学生にしては良く出来た歌詞だよな。
おそらくどこかに出典元があるのだろう。
七不思議というわりに4つしかないので、続きがあるのかもしれないが、あいにく自分のところにはここまでしか伝来してこなかった。
惜しいな。
ところが、ある時代を境目に、この曲を取り巻く状況は一変するようだ。
「ぐんかんマーチ? なにそれ。うまいんか?」
この曲を全く知らない、という世代にスッパリと切り替わるのだ。
こんな統計を取った人間はいないと思うので、感覚的なものに過ぎないが、おそらく、平成に入ってから生まれた世代あたりからだと思う。
ウソだと思うなら、平成生まれの人間に聞いてみるといい。
保証はしないけど、たぶん知らないから。
いわれてみれば、もう長いこと、テレビや街で軍艦マーチを聞いた覚えがない。
軍艦マーチを改めて聴こうと思い立ちもしないから、昭和世代の記憶の中だけにそのメロディーが記憶されるにとどまっているものと思う。
 ネットの拾い物(いけません)
ネットの拾い物(いけません)
まぎれもない軍歌のはずなんだけど、なんだか不思議な曲だと思う。
「軍隊」というものが、ある種タブー視されているこの日本という国にあって、何の違和感もなく、戦後何十年たっても巷で独り歩きしていたことが何より驚きだ。
そもそも「軍艦」なんて物騒な名前がついているけど、これが軍歌という認識はほぼなく、どちらかというと、あっけらかんとした平和なイメージを持っていた。
これは、現代における、すしネタの「軍艦」に、軍事色を全く見出さないのに似ているのかもしれない。
替え歌ではない本来の歌詞からして、「♪守るも攻むるも くろがねの・・・」と、受け身から入っていることが、変テコリンさを増幅させている。
例えば、フランス国歌でもある軍歌『ラ・マルセイユ』*2()が、
「♪Allons enfants de la Patrie, Le jour de gloire est arrivé !」
(祖国の子らよ 栄光の日の到来だ!)
と意気高らかに宣言するのに比べ、何とおとなしいことだろう。
「♪守るも攻むるも 黒鉄の 浮かべる城ぞ頼みなる」
(守るにしても攻めるにしても実に頼りがいのある、まさに海に浮かぶ城と呼ぶべき鉄塊!)
「♪浮かべるその城日本の 皇国の四方を守るべし」
(日本の海に浮かぶこの城は、国家の全方位をも守るといっても過言ではない)
もちろんこのあと、守るだけではなく攻めるんだけど、
「♪仇なす国を 攻めよかし」
(危害を加えてくる国には、攻めてやれってもんじゃね?)
と、どこまでも受け身である。
カッコよく言えば、後の先を取ることを信条としているといってよい。
そして2番は機関や大砲などの装備自慢に終始するため、むせっかえるほどの男臭さはあっても、血なまぐさいところがほとんどない。
これで意気を揚げるのに有効だったんだろうか甚だ疑問だ。
軍歌なのに。
やっぱりそれじゃいけないと軍部が思ったかどうかはいざ知らず、歌唱を伴うときには、万葉集からとった「海ゆかば」の部分をオマケのようにつけて演奏されることが多い。
その部分は、モチ、お国のために死にますぜ?という内容で*3、
内容的に決して褒められたものではい。
余計なものを取って付けおってからに。
意味が知りたい★ここんとこ 深読み&ななめ読み
黒鐵・眞鐵
どちらも鉄を指す言葉で、鉄の組成的・構造的な分類ではなく、どちらかというと印象としての鉄の分類。
黒光りするような鉄の大きな塊を「くろがね」といい、頑強なイメージを持つ言葉。
「まがね」は、同じく鉄を指すが、張りぼてではない正真正銘の鋼のイメージを持つ。
石炭
石炭と書いてイワキと読む。
もとは木のような石、という意味合いで「石木」と書いたらしい。
磐城国(現在の福島県浜通り地方)とは、語源が同じ可能性があるだけで、おそらく直接の関係はない。
わだつみ
海神のことだが、ギリシャ神話のポセイドンではなく、日本神話に出てくるイザナギ・イザナミ夫妻の子。
この歌に出てくるわだつみは、単に海原を指している。
どよむ
淀むの誤記ではなく、漢字で書くと「響む」。
現代では「どよめく」という表現の方がよくつかわれる。
意味は漢字で書いた通り、響き渡ること。
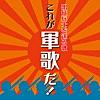


![「行進曲」-世界に冠たる日本のマーチー [ 武藤英明 ロンドン・フィル ] 「行進曲」-世界に冠たる日本のマーチー [ 武藤英明 ロンドン・フィル ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6884/4526977006884.jpg?_ex=128x128)